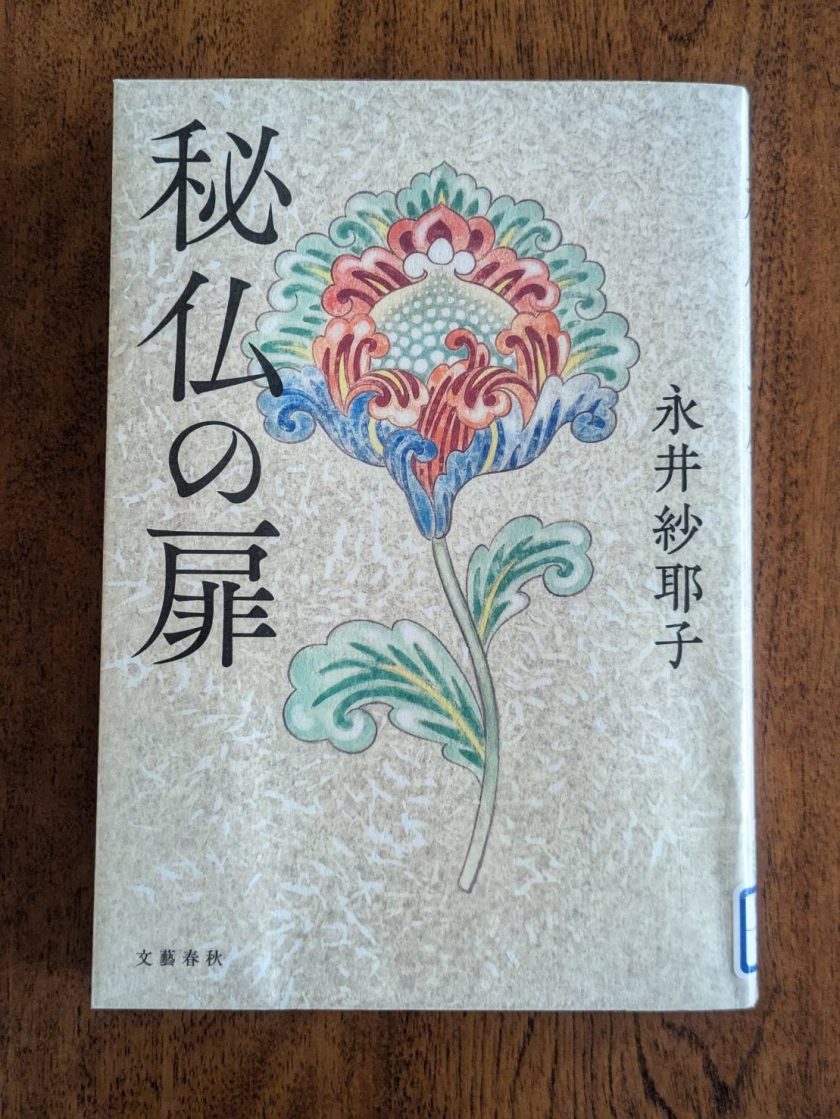永井紗耶子著『秘仏の扉』(文藝春秋)を読む。
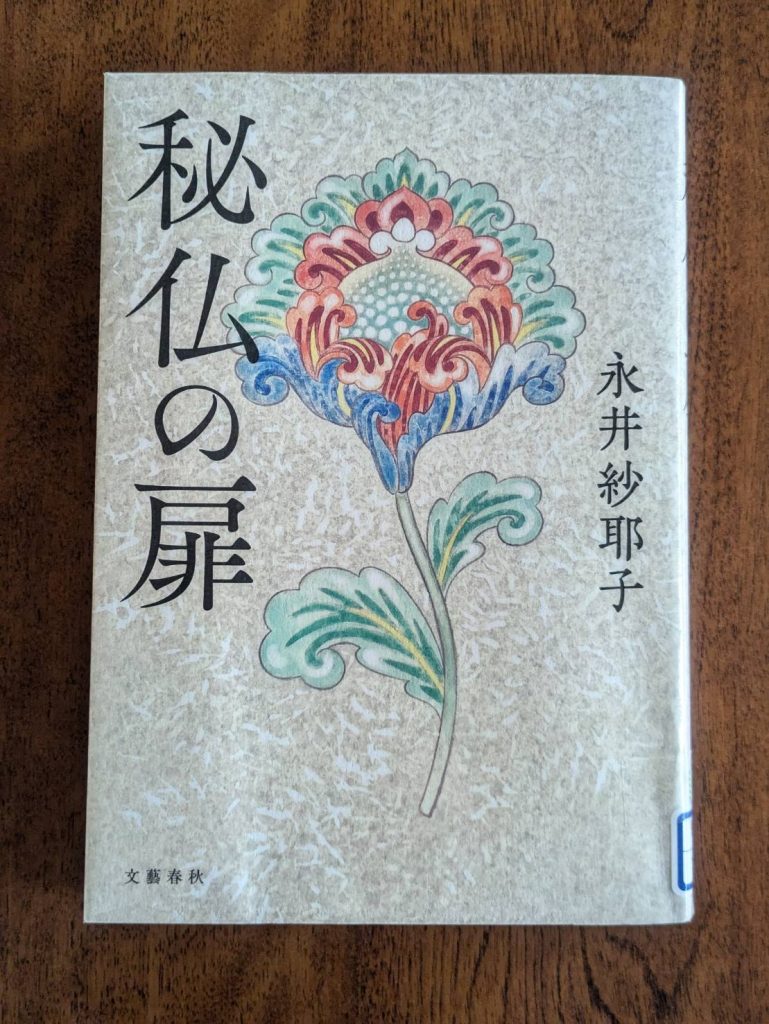
明治新政府は、神道国教化の方針のもと、1868年に神仏分離令を出した。
それまで当たり前であった神仏習合を禁止し、神道と仏教、神社と寺院を明確に切り離したのだ。
これを機に、廃仏運動が激化し、全国の寺院や仏像の破壊が広がってしまう。
このような中、日本の仏教や仏教美術のすばらしさを伝えた男たちがいた。
写真家の小川一眞、官僚の九鬼隆一、法隆寺の千早定朝、東洋美術史家のフェノロサ、思想家の岡倉天心、官僚で後に僧侶となる町田久成である。
この6人の物語が『秘仏の扉』だ。
この小説は6章からなるが、各章で一人の人物を扱っている。
同時期の出来事をそれぞれの視点で描いているところがおもしろかった。
彼らがいなかったら、寺院や仏像などの日本美術は消えてなくなっていたかもしれない。
彼らのやった仕事は非常に偉大だった。
この中には、家庭人として問題ある人物も複数いるのだが。
寺社仏閣好き、仏像好きの私としては、『秘仏の扉』は最高の小説だった。