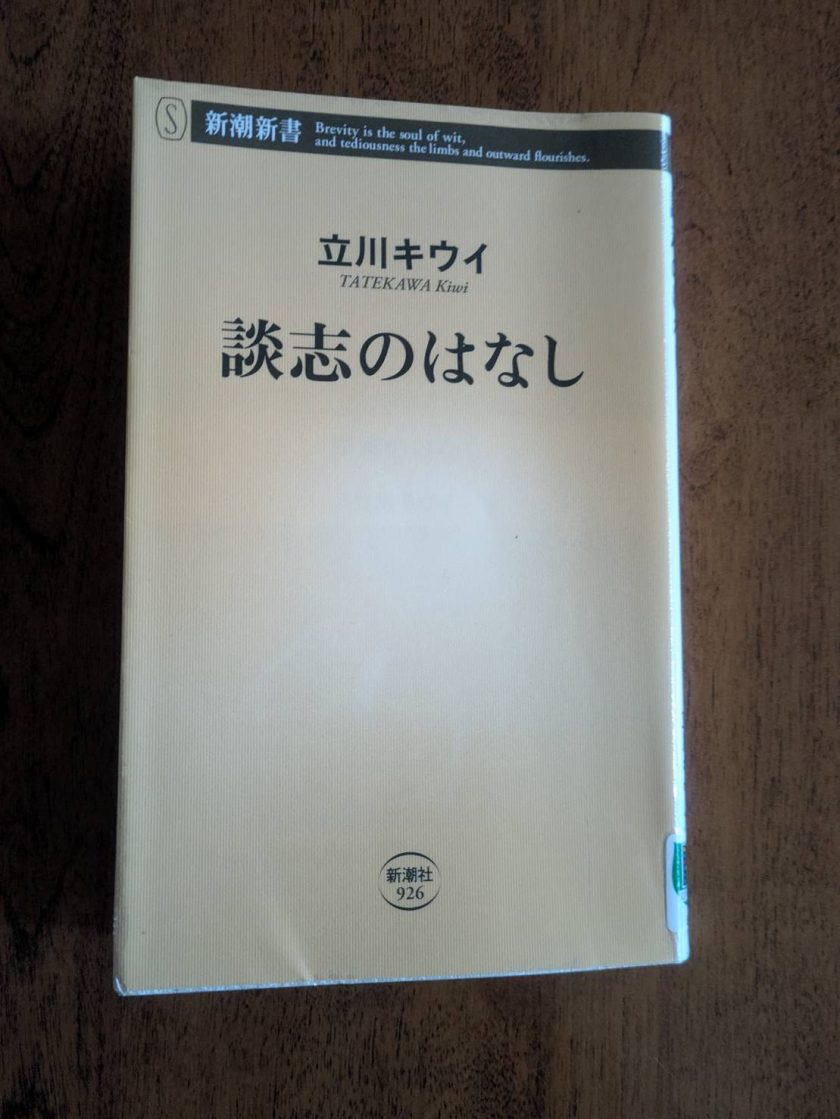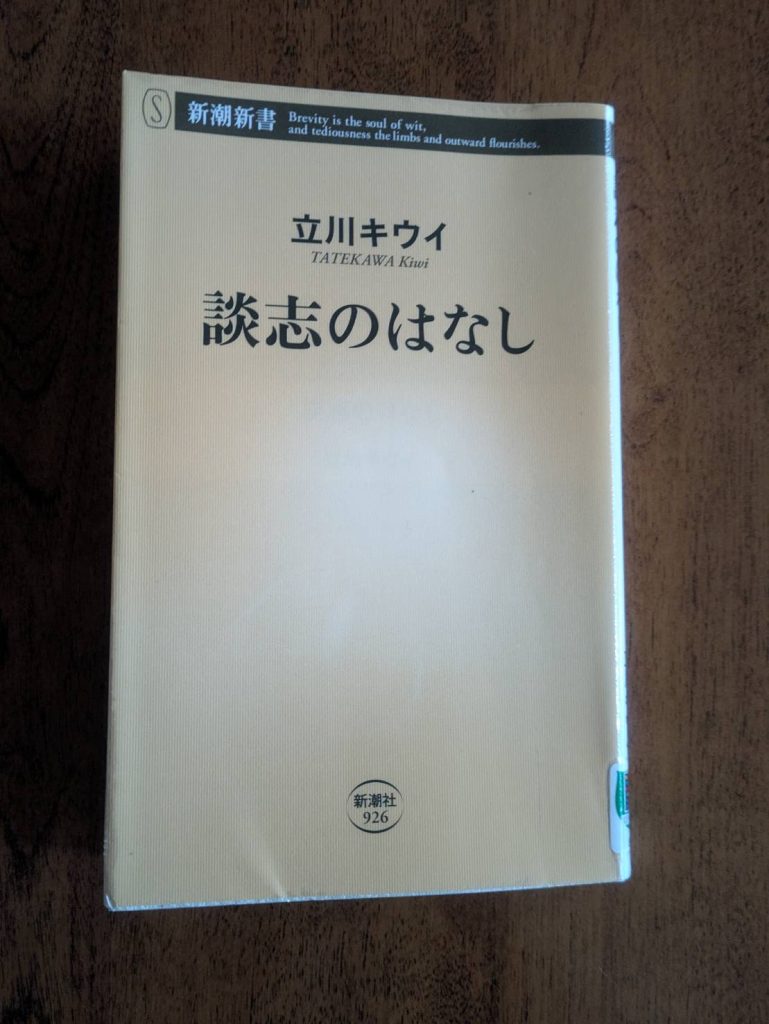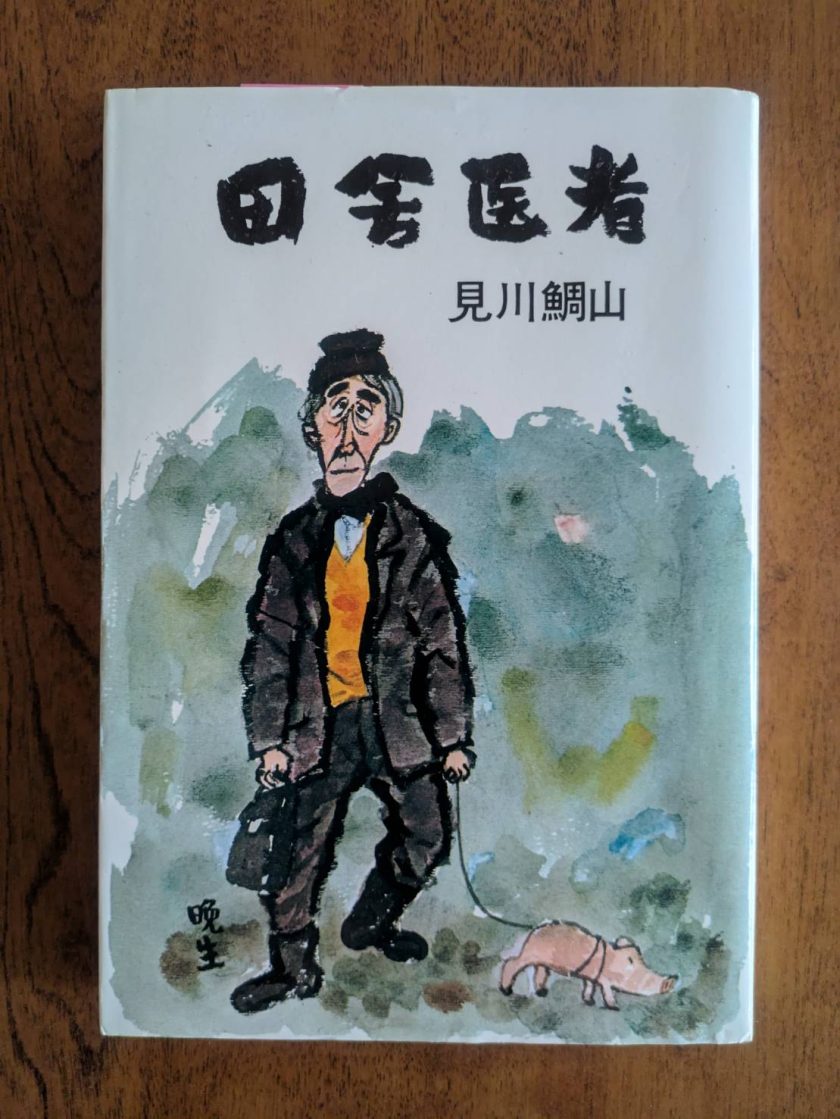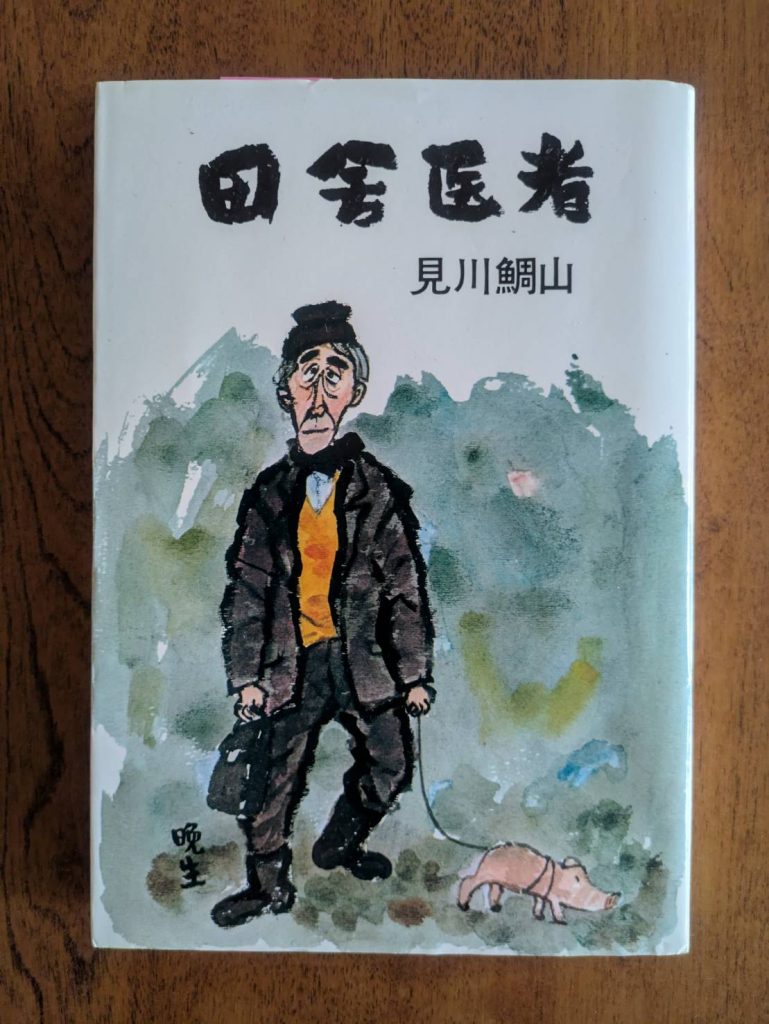拙文「開塾30年 より良い教育に」(ブログ第218回)について、保護者様から心温まるご感想をいただきました。掲載の許可をいただきましたので、ご紹介いたします。本当にありがとうございました。
今年、開塾30年おめでとうございます。
どれだけ便利な世の中になっても、人間と人間のコミュニケーションは大切ですね。
本当にそう思います。
(Aさま)
新年下野新聞の投稿みました。
長きに渡り子供たちの教育発展のためにありがとうございます。
子供が尚朋スクールに通ったおかげで、勉強の仕方がわかり、学ぶ意欲がでたことに感謝しています。
どうかこれからも、ご夫婦でお身体に気をつけて子供たちをよろしくお願いいたします。
(Bさま)