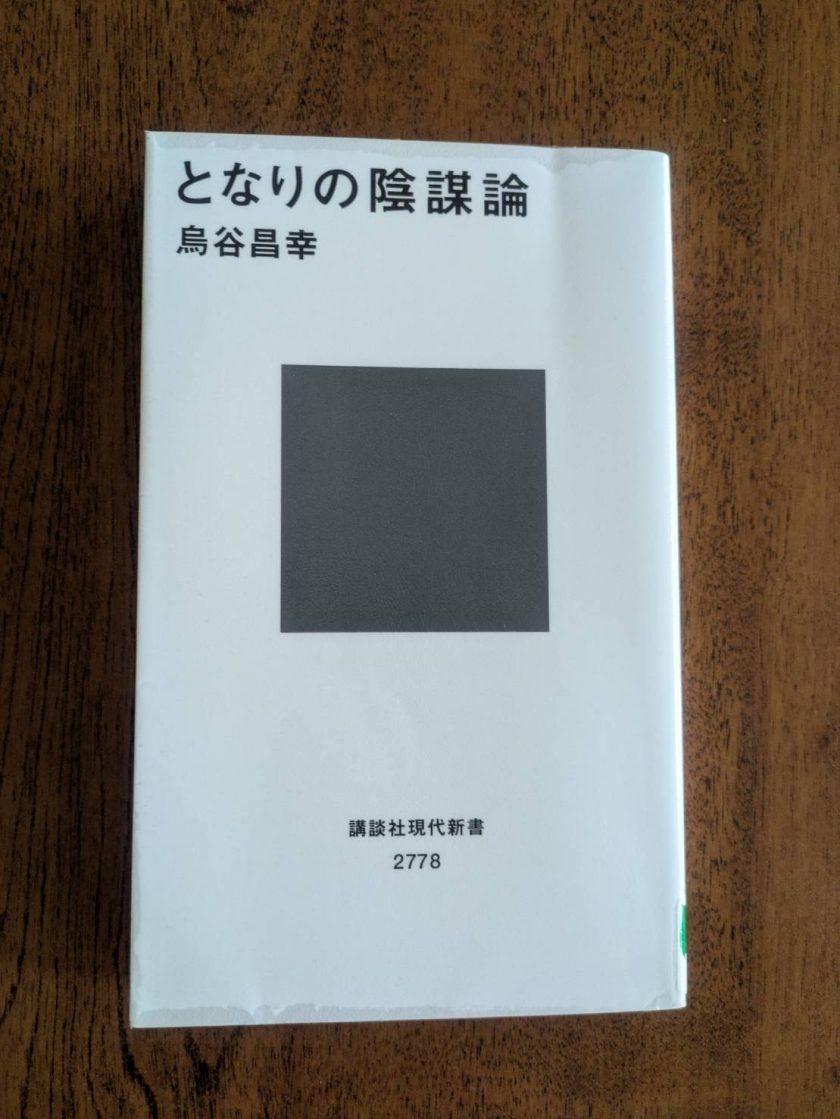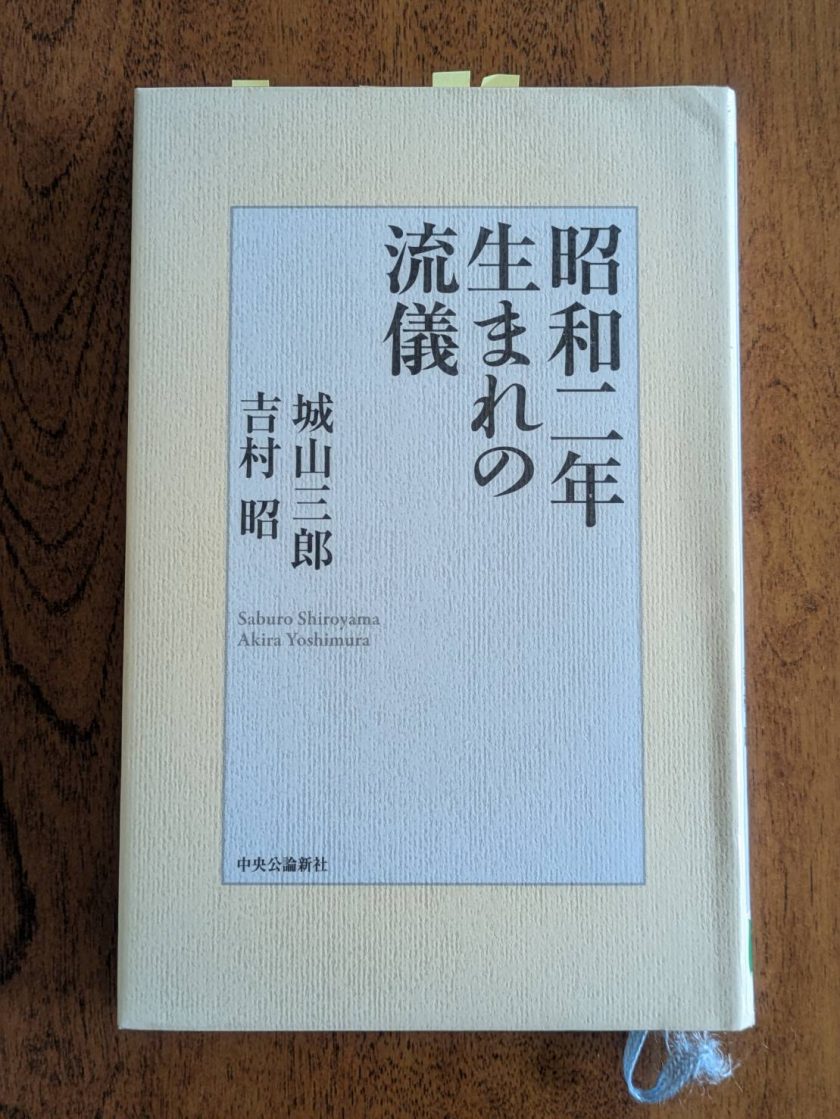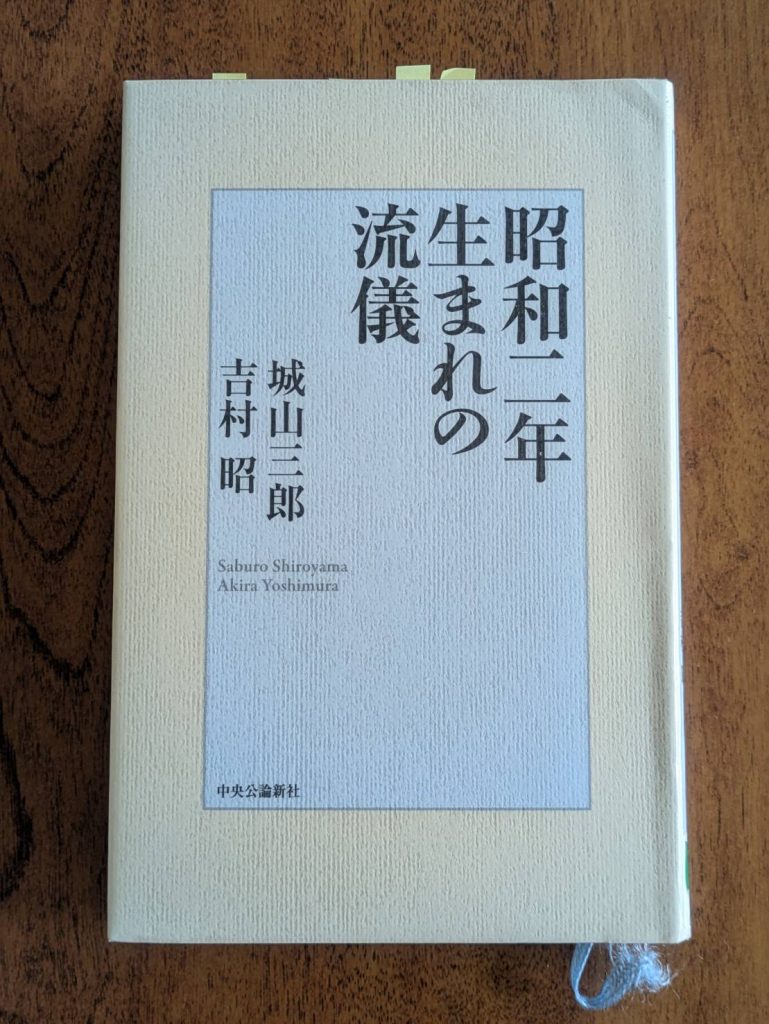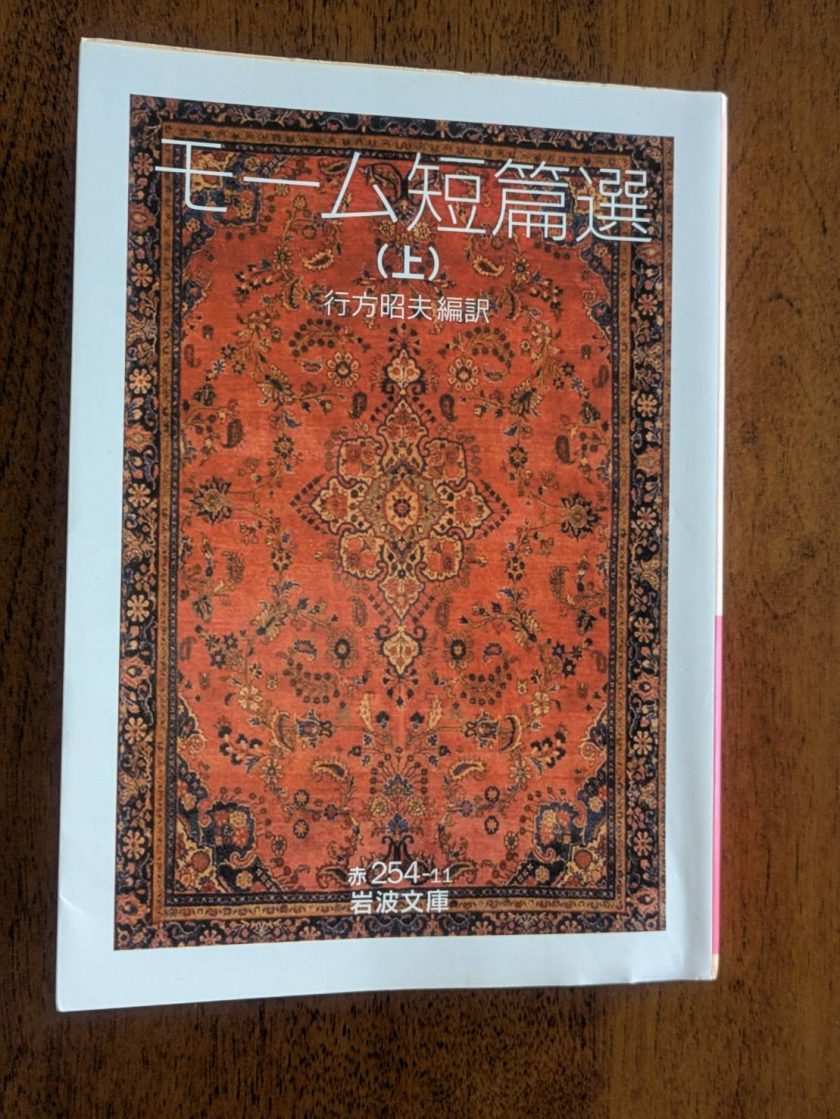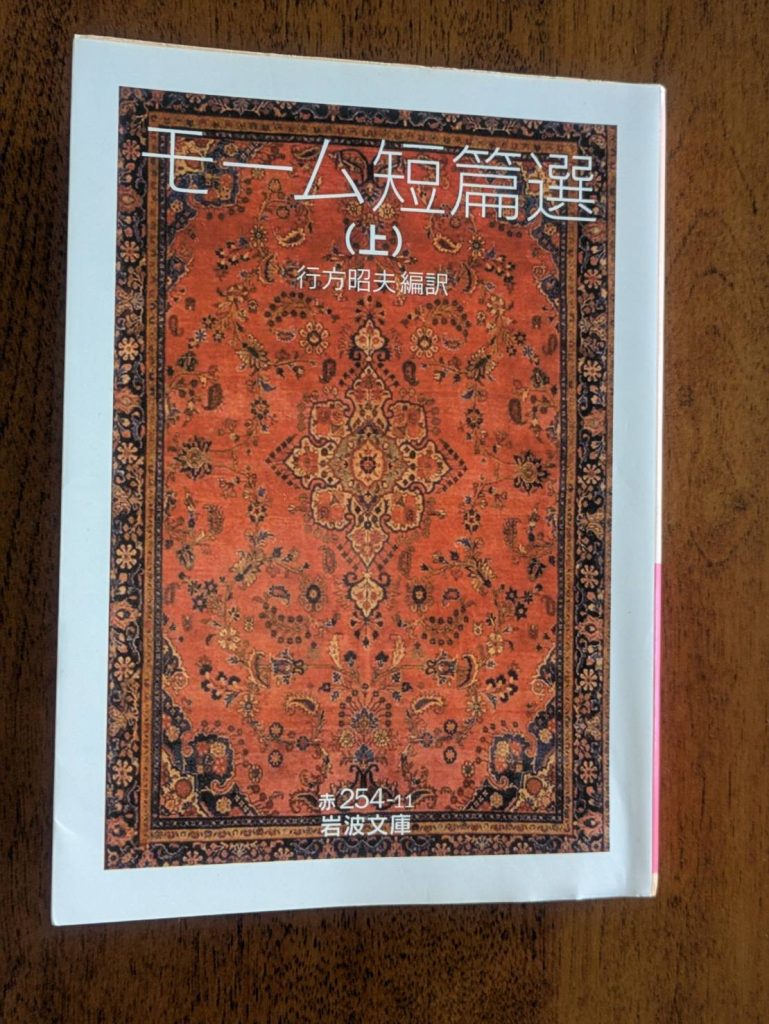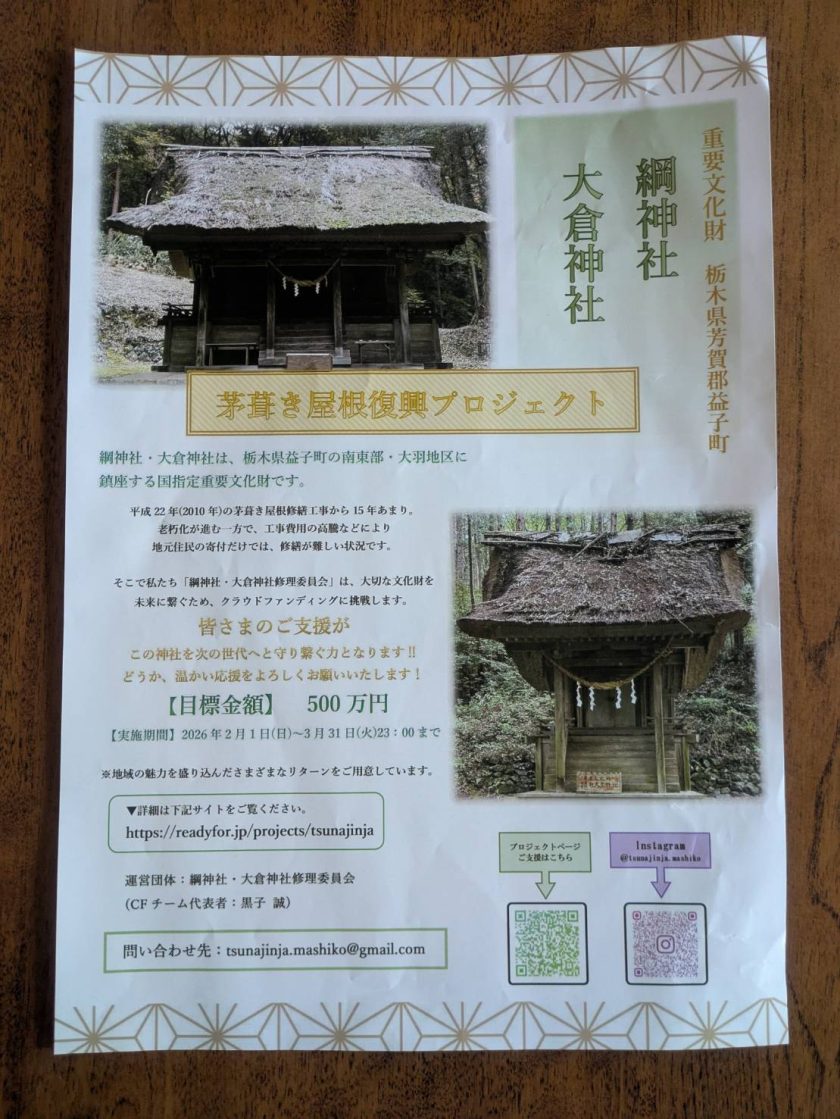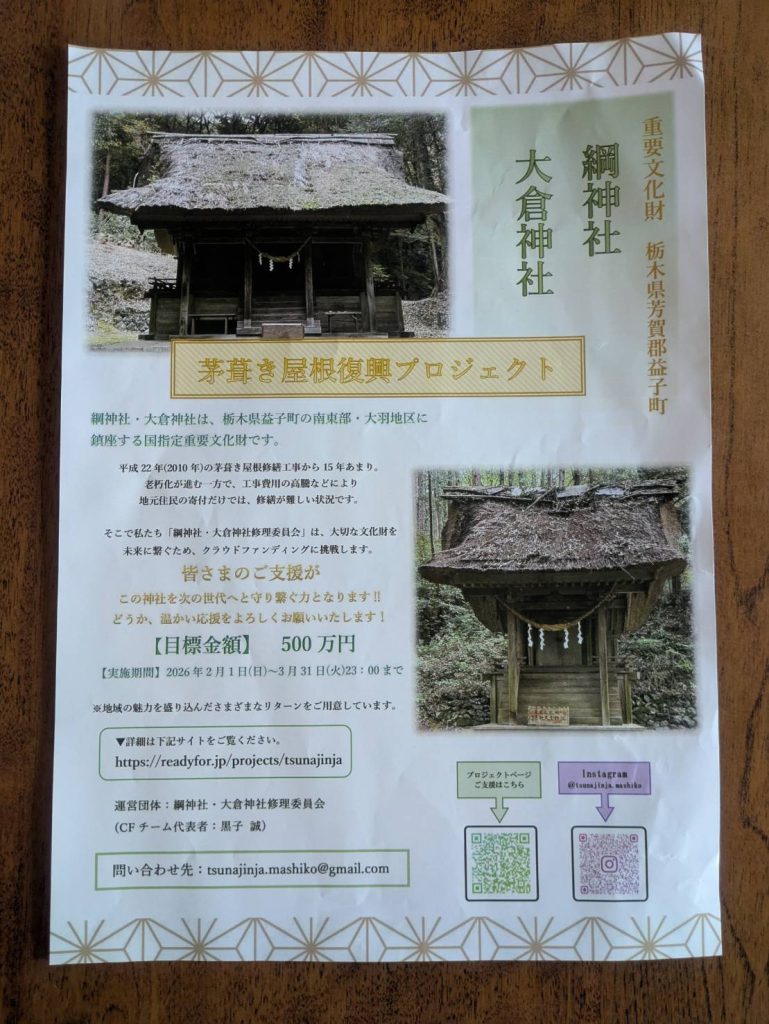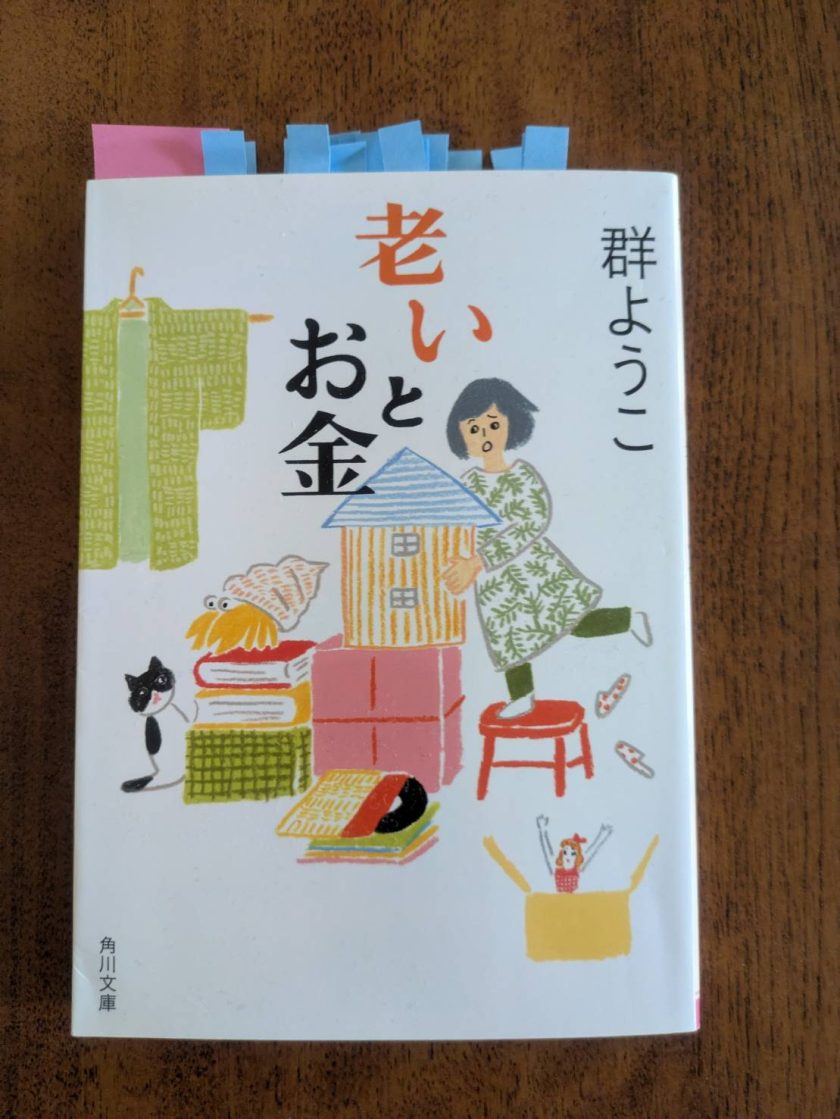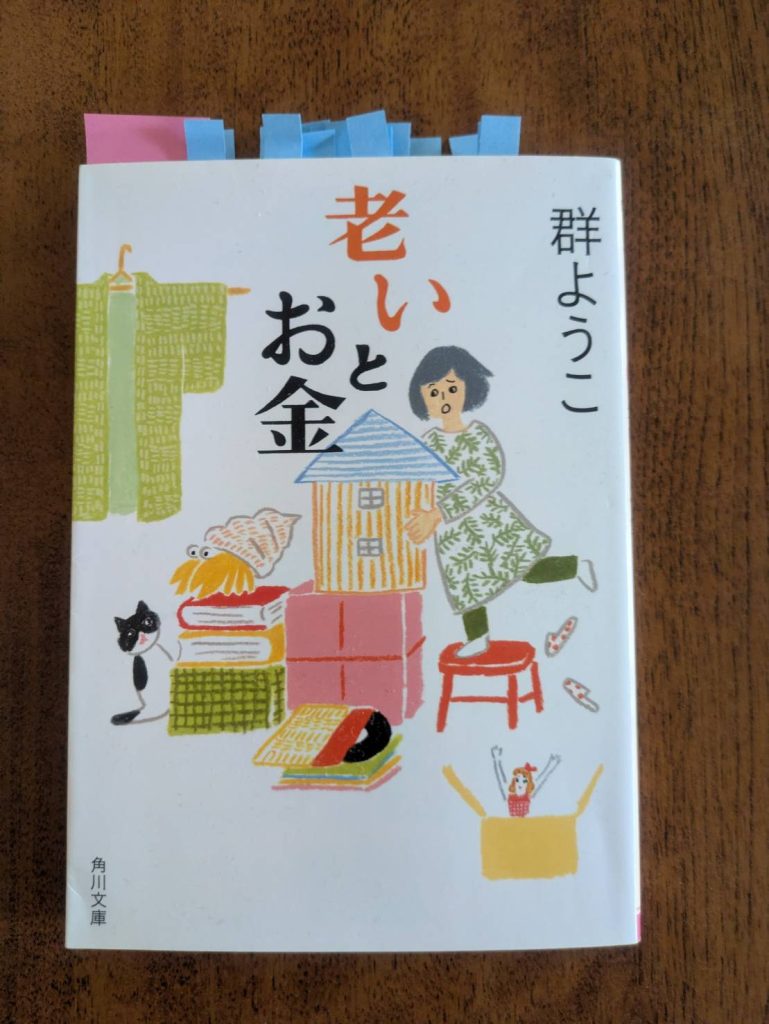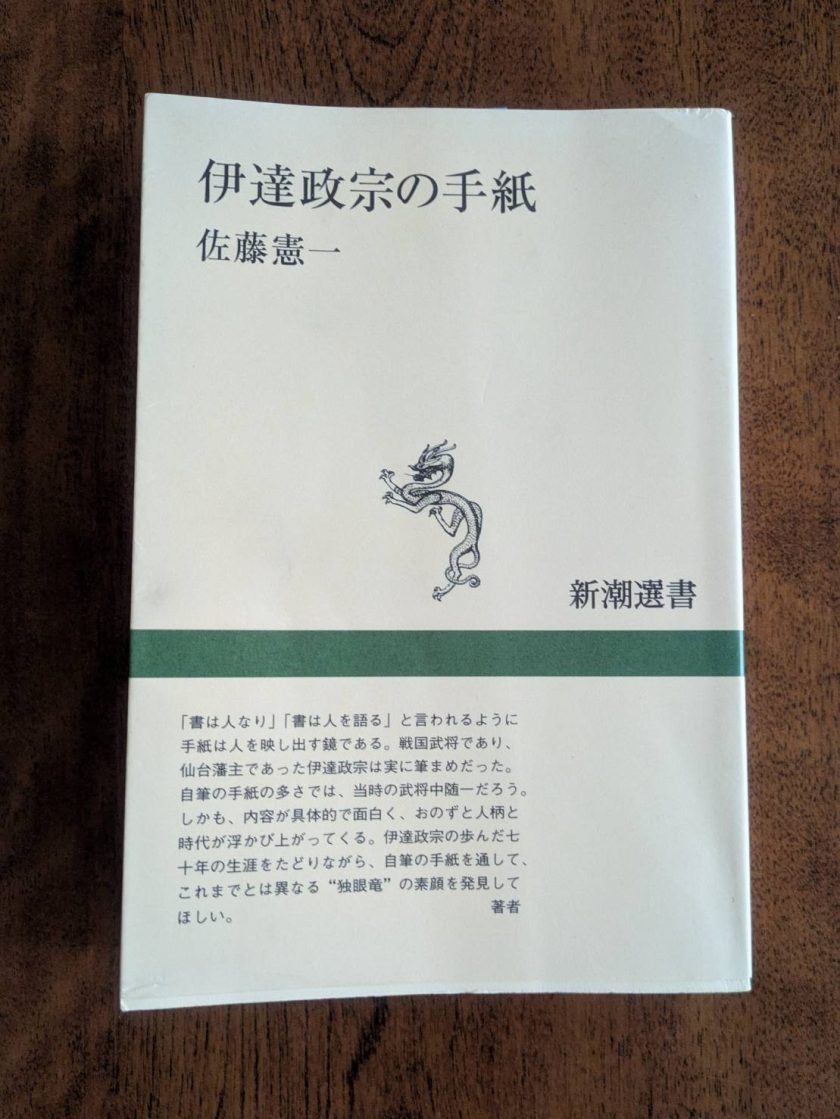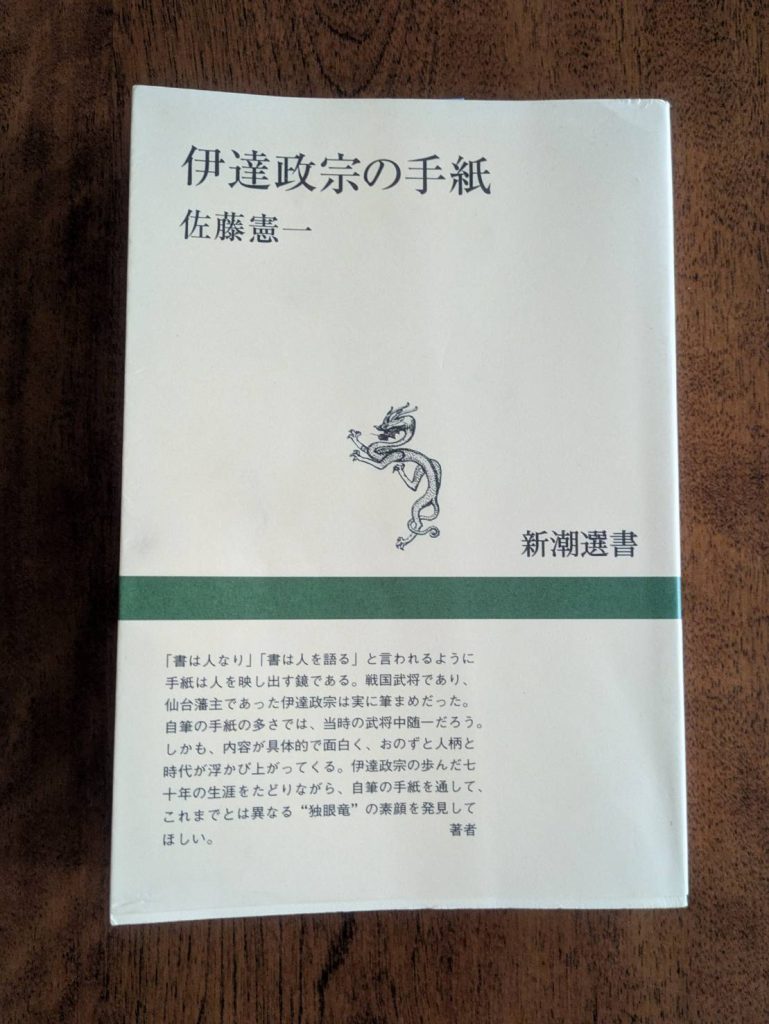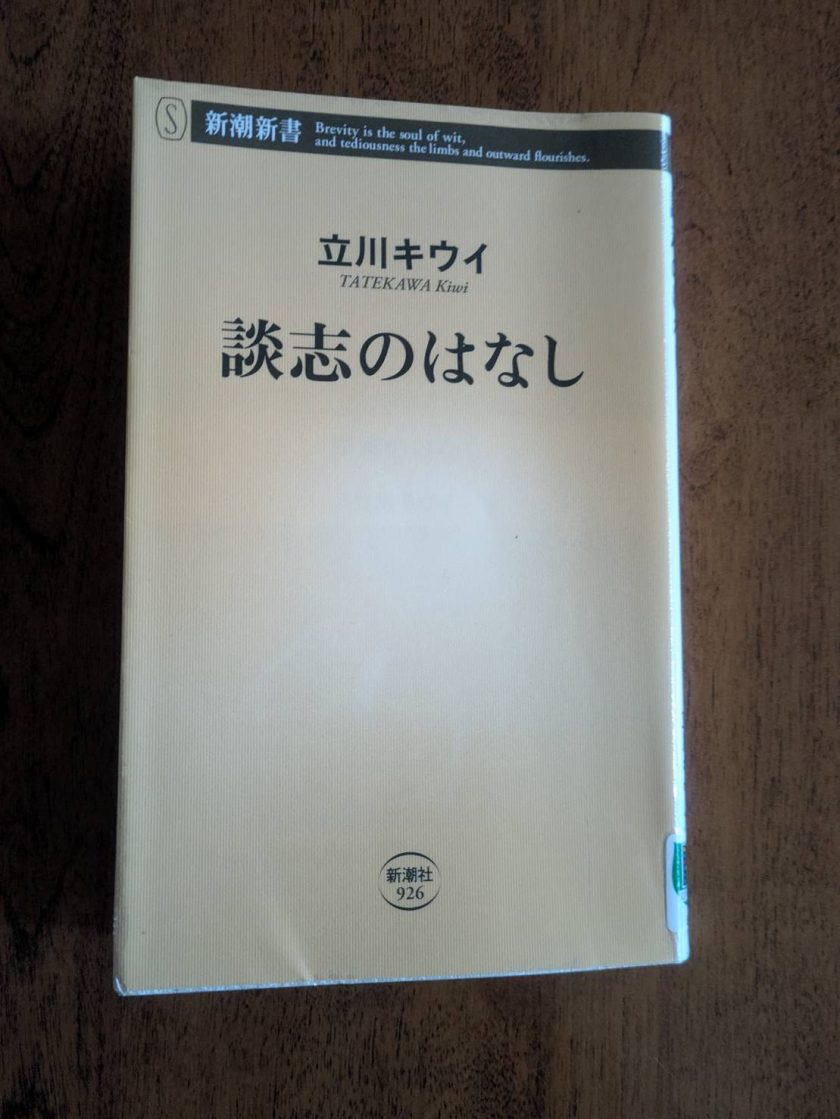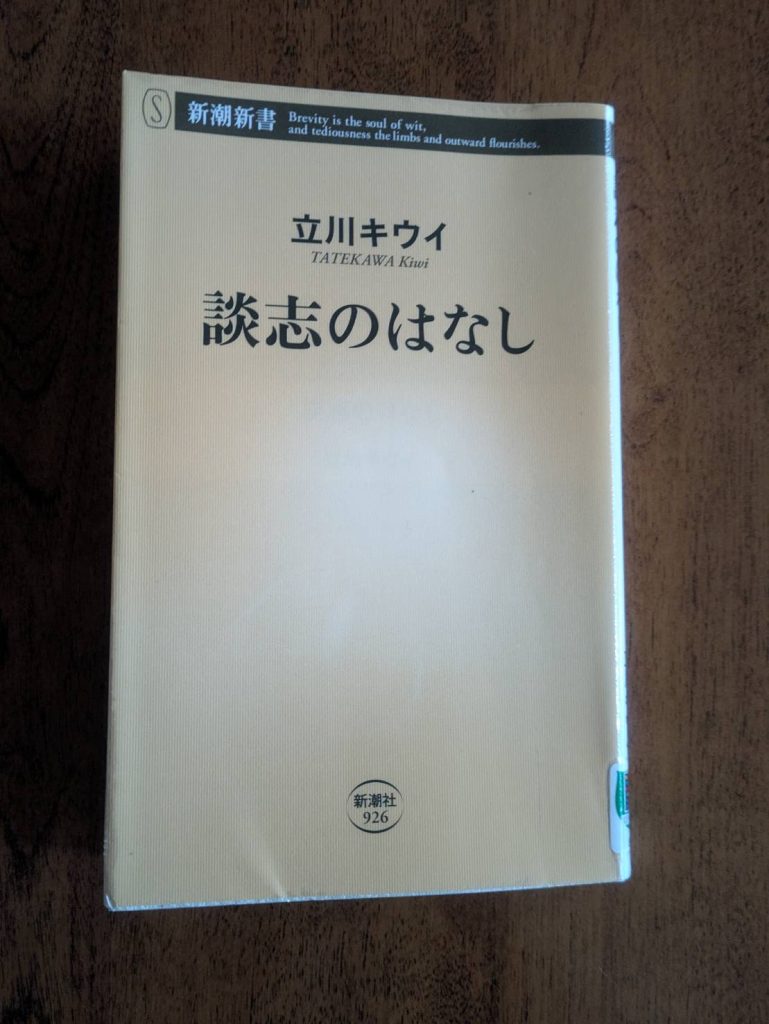烏谷昌幸著『となりの陰謀論』(講談社現代新書)を読む。
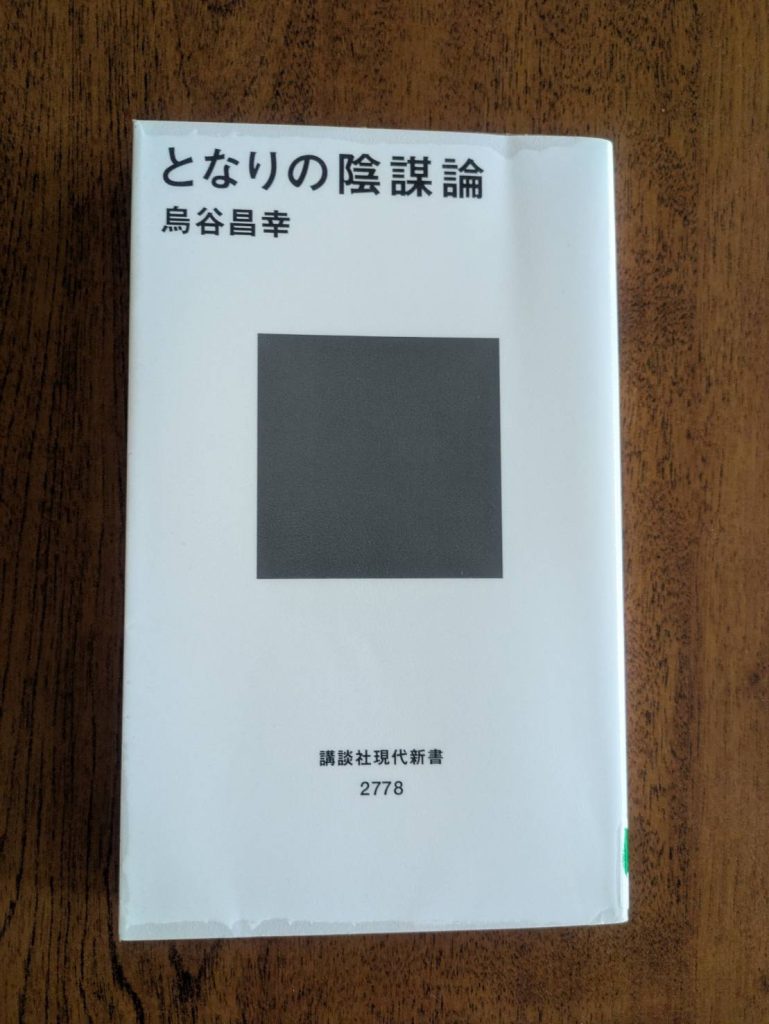
この本は以下の四章からなっている。
第一章 陰謀論とは何か
第二章 陰謀論が生む「パラレルワールド」
第三章 「陰謀論政治」はなぜ生まれるのか
第四章 陰謀論を過小評価してはならない
著者は本書で、陰謀論を歴史的な視点も踏まえて丁寧に解説する。
そして、陰謀論を甘く見てはいけないと語り、「陰謀論研究の裾野を広げていく必要がある」と結論づけている。
陰謀論が政治に悪影響を及ぼしているのは、トランプ独裁が進むアメリカを見ればよくわかる。
残念ながら、世界も、そして日本も同じような流れになっている。
陰謀論が大きな問題となり世界を変えてしまったのは、インターネットの普及が大きい。
たいへん便利なインターネットだがマイナス面も大きいのである。
しかし、もうインターネットのない世界には戻れない。
この先、世界はどうなってしまうのか?
正直、とても不安である。
多くの人が「陰謀論とは何か」ということを考え、研究者が書く本(専門書ではなく本書のような一般向けの本)を読むことが必要なのではないだろうか。
その意味でも、本書は最高の入門書だと思う。